| ~1961.7.31 | 1961.8.1~1972.1.22 | ||
| Heads | Tails | Heads | Tails |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | 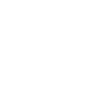 |  | 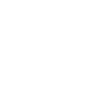 |
 |  |  | 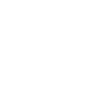 |
 |  | ||
このページでは1957年以降の市電の系統板の表・裏の組み合わせを整理します。
「回送」「貸切」「故障」は白無地の円板(以下(白)と表記)を使用したので,(白)も意味のある円板であった。(白)と終電を表す(終),試運転を表す(試)の円板は全ての車庫に共通であったが,他の円板は車庫別に色分けされていた。ただし(試)の円板は全ての車庫で常備していたか否かは疑わしく,時代が下がると烏丸以外では消滅したようである。(その代わり急行板サイズの「回」とか「試」が用意されていた。)
京都では終電は系統に関してではなく,交差点間での最終電車として定義された。従って特定の交差点間を(終)の円板を表示して走る電車は各方向1両だけである。それ以外の区間は(臨)表示となるため,(臨)と(終)を表・裏にするのは便利に思えるが,「臨終」など縁起でもないと思ったのか,この組み合わせはそれほど多くはない。しかし下の表にある以外にも散発的に目にする機会があった(ただし壬生と烏丸では見たことがない)。
| ||||||||||||||||||||||||||||
北野線廃止後は10・11系統は一体運用となり,京都駅と白梅町で(10)→(11)または(11)→(10)に系統変更する必要があったため,これが組になるのは当然である。結果的に21系統が半端となった。なお末期に(21)の裏が(臨)になっていたこともあるが,(21)と(臨)の間の関係はそれほど深いと思えない。
|
4系統と6系統の操車は京都駅前西のりばでも行われ,ワンマン化以前には(4)と(6)の間の系統変更は頻繁に行われた。15系統は元々5系統の亜系統であり関係が深いため,(5)と(15)が組になるのは自然である。従って(14)が半端となったが,阪急河原町延伸に伴う系統変更で14系統が廃止になり13系統が錦林から移ると,(13)が半端となり裏は(白)であった。しかし13系統の円板は,烏丸車庫を出てから戻るまでに(臨)→(13)→(臨)と変化するため,(13)と(臨)をまとめてサボ差しに入れることが常態化した結果,暫くして(13)の裏も(臨)となった。 1964年に2000型・2600型ワンマンカーが登場すると,これは4系統の限定運用だったので,ワンマンカーに限り(4)と(臨)が組になった円板が使用された。しかし連結車の運行範囲が拡大され,百万遍・たかの-京都駅系統などは6系統として運行されたので,すぐに通常の(4)と(6)が組になった円板に変更された。1970年1月15日までは,5・13・15系統にはワンマンカーは入らなかったので,一部の円板は不搭載であった。 烏丸線廃止に伴い15系統が廃止になり,16系統が九条から移ると,単純に(5)の裏の(15)が(16)に置き換えられたが,(5)と(16)の関係は薄い。烏丸線廃止当初は,(4)(6)は烏丸車庫前で乗客を降ろしていたが,暫くして公式に(時刻表上も)連続運行されるようになった。このため一部を除いて京都駅と烏丸車庫で(4)→(6),(6)→(4)の系統変更が原則となった。 最後の1年は22系統は烏丸に移った。現物を見ていないので確認できないが,(6)と(22)が組になった円板が使用され,(臨)は(13)の裏が使われたようだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九条車庫の7系統と8系統は戦前のむ・め系統の流れを引く循環系統で,車庫前での系統変更はよく見られた。これに対して17系統の循環系統としての歴史は浅く,運転本数も7・8に比べて少なかったので,(7)と(8)が組になるのは当然と言える。 伏見線では,18系統は中書島で9系統へ,9系統の一部が中書島で18系統に系統変更された。京都駅八条口では京都駅行の電車に対し,京都駅からの折り返し系統番号が指示されたが,多くの場合円板は八条口出発時に変更された。従って(9)・(19)の系統変更も多く行われたので,(9)の裏は(18)・(19)の何れでも良いようなものであった。結果的に(9)と(18)が組となり,余った(19)は九条車庫で半端となった(17)と組になったが,この両者間の系統変更の可能性は皆無である。 伏見線が廃止になると,22乙系統が錦林から移った。当初は錦林の表裏(22)の円板をそのまま使用したが,九条所属車が錦林の円板で走るのを見るのは奇異な感じであった。この時代,22系統には甲・乙ともワンマンカーは入らなかったので,錦林のワンマンカーに搭載されていた円板を,九条のツーマン車に搭載したものと思われる。数ヶ月遅れて九条色の(22)の円板が登場するが,この時点では裏は(白)であった。九条の22系統の円板は,九条車庫を出てから(臨)→(22)→(臨)と変化するので,この場合もサボ差しに円板を2枚入れることが常態化し,ほどなく裏側は(臨)に変更された。この段階では(19)は不使用である。
なお1974.4~76.3の間,(8)のフォントが右写真に示すコンデンス体になっていたことは,下の錦林の系統板における縁の有無同様,撮影時期の特定に役立つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今出川線が全通し22系統が甲・乙別の円板を使用するようになる以前は,(13)の裏が(22)になっていたかどうか定かではないが,(12)の裏は(2)と(13)の2種類があった。京都駅から来た2乙系統の相当部分は,錦林車庫で西大路四条止まりの12甲に系統変更されたから,(2)と(12)は関連が深い。一方13系統は12乙系統を使って出入庫していたので,円板は(12)→(13)→(12)の順に変更されるからである。しかし同一系統番号とは言え,22系統の甲・乙通し運転は極めて珍しいので,表・裏(22)というのが実は一番関連が薄かった。 阪急河原町延伸に伴う系統変更で13系統が烏丸へ移ると,そのまま円板は1枚削減になった。さらに伏見線廃止に伴い22乙系統が九条へ移ると,ワンマンカー搭載の(22)の円板は九条に引き継がれることになる。 壬生車庫の廃止により22系統は九条の循環系統となり,白梅町-円町間の重複走行はなくなったが,代わって12系統が円町-西大路四条間を重複走行するようになったため,(12)の円板が甲・乙の2種類になった。この時点では(12)を1枚にして(2)の裏が(白)とされたが,実際には12系統の甲・乙通し運転より,2乙から12甲への通し運転の方が多かったため,最後には(2)と(12)の組み合わせに戻された。 錦林の円板は元々3色使用であったので,経費節減のためか壬生車庫廃止時点に縁なし塗装となり(12乙系統の円板についても白縁を省略),(終)も赤字から黒字に変更された。これでは締りがない,と思ったせいか,烏丸線廃止時点に縁が復活したが,2色使用のため「黒枠」となった。錦林車庫及び市電の運命を暗示するようだ,と噂したものである。同時に(終)にも縁が復活したが,以前のようなピンクではなく「赤枠」であった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Scroll Signs of Kyoto City Trams
Scroll Signs of Kyoto City Trams Route Numbers and Color Codes
Route Numbers and Color Codes Gleanings from Trolley Days
Gleanings from Trolley Days |
 |
 |